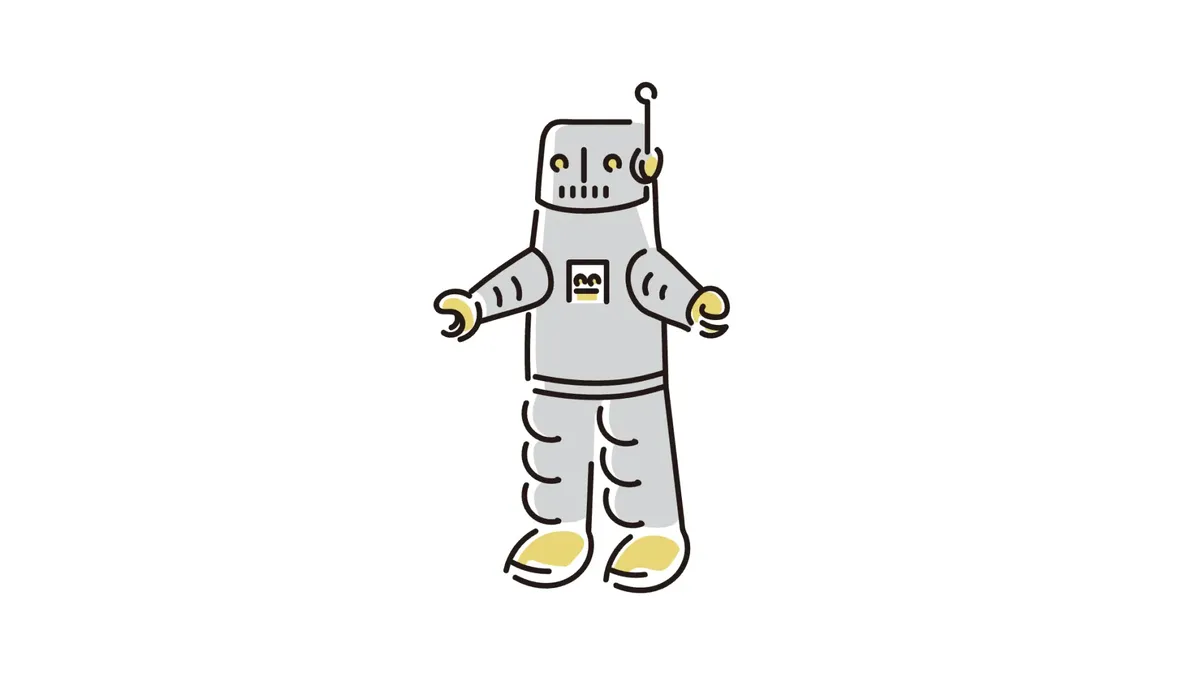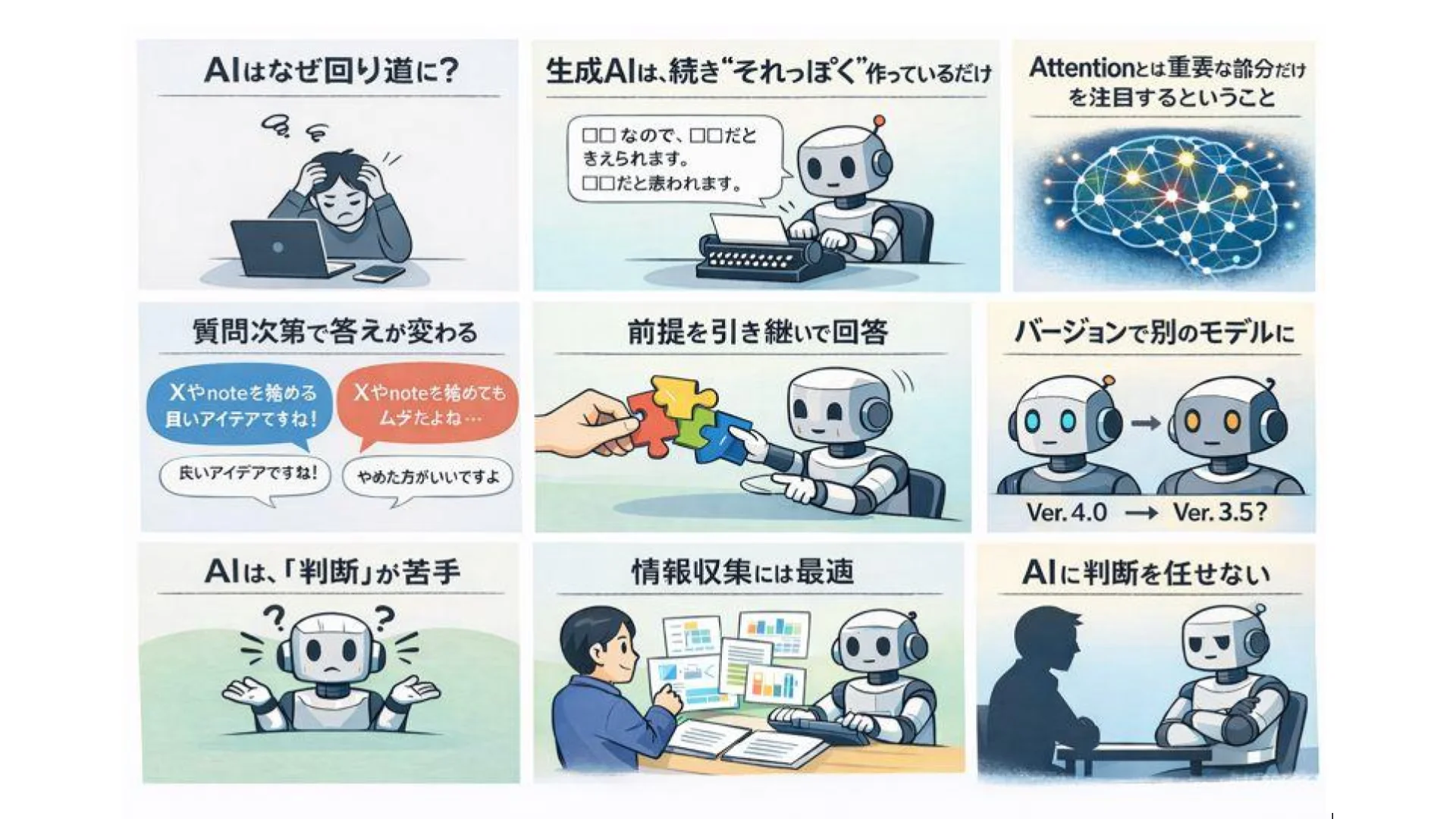「AIが進化したら、プログラマーは不要になるのか?」
誰もが一度は考えるこの問いに、僕はここ半年ずっと悩まされています。
きっかけは、業務で Microsoft TeamsのCopilot を使い始めたこと。
コードの仕様調査から文書作成まで、自分が何時間もかけていた作業が一瞬で片付きます。
その衝撃は、「あれ、これもうプログラマーいらなくなるんじゃないの?」と思わせるほどでした。
Copilotが変えた日常
実際にCopilotを使っていて、一番大きな変化は 「コードを読まなくなった」 ことです。
以前なら、システムの調査や改修をするために、自分でPGMを読み込んで仕様を理解する必要がありました。
でも今は、コードをテキスト化してAIに読み込ませ、「この処理は何をしている?」と聞けば答えてくれる。
結果として、プログラミング経験が浅い人でも、AIの助けを借りて対応できる範囲が広がりました。
「プログラマー不要論」が現実味を帯びてきたのは、この瞬間でした。
プログラマーに残る価値とは?
では、AIがここまでできる時代に、人間のプログラマーは何をするのか。
僕は大きく3つの領域に価値が残ると考えています。
1. 本当に必要な仕様を決める力
- AIは与えられた仕様を整理するのは得意ですが、「何を作るか」は決められない。
- 顧客の要望や制約の中で優先度を判断できるのは人間です。
2. 人と調整し、合意を形成する力
- 開発は合理性だけで進まない。組織の力学や人間関係を踏まえた調整はAIには難しい。
- すべてを完全に言語化できればAIでも可能かも知れませんが、その言語化こそが人間にしかできない難しさです。
3. システム全体を設計する力
- AIは「こう作れ」と言えば最適解を返してくれるけれど、その“問い”が的外れなら意味がない。
- 保守性や拡張性を意識して、AIに正しい問いを投げられる力が必要です。
AI活用のリスクと落とし穴
AIは強力な武器ですが、無批判に使うと大きなリスクがあります。
- セキュリティリスク:Copilotが提案するコードには脆弱性が含まれることがあります。そのまま採用すれば、思わぬセキュリティホールを生む可能性があります。
- 品質のばらつき:出力は一見正しそうに見えるだけで、実際は業務要件を満たしていないことも少なくありません。「正しそうに見える」のが一番厄介で、人間によるレビュー力がますます重要になります。
- 依存性の高まり:自分で考えずにAIに頼る習慣がつくと、基礎力が衰えるリスクがあります。個人としても組織としても、これは長期的な弱点になりかねません。
つまり、AIを使えば使うほど、レビュー力・判断力といった“人間の基礎力”がより問われる ようになるのです。
オフショアとAI時代の労働構造
もう一つ気になっているのが、オフショアやパートナー会社の人材は今後どうなるのか という点です。
実務で一緒に仕事をしていると、よくこんな光景を目にします。
「自分、Java少しできますけど仕事ないですか?」
「マクロ組めますけど、何かやることありますか?」
──そういう“街で仕事を待っている”ような人たちです。
これまでは、そうした人に小さなタスクを振り分けて開発が成り立っていました。
しかしAIがタスク処理を圧倒的なスピードでこなすようになると、10人で分けていた仕事を、1人+AIで回せてしまう のです。
結果として「仕事待ち型のエンジニア」は確実に余剰化します。
そして彼らが生き残るには、単なる作業者から“何を作るべきかを考える人”に進化する必要がある と思います。
- 今どんな機能があれば会社の利益につながるのか
- 顧客にとって本当に必要なのは何か
- そもそも作るより買った方が安いのではないか
こうした“上流の問い”に関われないと、AIと競合する形になり淘汰されてしまうでしょう。
僕自身の考えとしても、オフショアは今後 「量で勝負する」から「質で勝負する」 方向にシフトせざるを得ないと思います。
単価の安さという強みはAIのスピードに駆逐され、業務理解やドメイン知識 × AI活用力 が生き残りのカギになるはずです。
教育と学び方のシフト
昔の新人教育は「とにかくコードを書いて覚える」スタイルでした。
しかしAIが初稿を出すのが当たり前になると、このやり方は機能しなくなります。
これから必要になるのは:
- AIの出力を理解する力
- 誤りを見抜いて修正する力
- 文脈に応じて応用する力
つまり「ゼロから作れる」よりも「AIが作ったものを正しく扱える」人材が求められるのです。
教育現場やOJTも、写経や課題演習から、プロンプト設計やコードレビュー演習へと変わっていくでしょう。
UdemyやYouTubeに「AI時代のコードレビュー講座」が出る日も近いかもしれません。
そして、AIをどう教育に組み込むかは業界全体の新しい課題になるはずです。
プログラマーからエンジニアへ
ここから先のプログラマー像は、「ただコードを書く人」から「AIを活用して価値を生む人」 へと進化していくと思います。
昔は「手を動かしてコードを覚える」ことが新人の学び方でした。
これからは 「AIの出力を理解し、修正し、文脈に合わせて使う」力 が重要になる。
言い換えれば、“プロンプト設計力=次世代の設計力” です。
これができる人は、単なるプログラマーではなく、AI時代のエンジニアとして生き残れるはずです。
これからプログラマーを目指す人へ
正直に言えば「AI時代にプログラマーで食っていけるのか?」という不安は残ります。
でも、僕はこう考えています。
- AIはコードを書く速度を圧倒的に速くする
- だからこそ 「AIが進まない部分」 を理解する人材に価値が残る
- そのために必要なのは基礎力です
- 開発環境を自分で構築できる力
- エラーを切り分けられる力
- Webアプリの基本構造を理解していること
これらを押さえていれば、AIは強力な武器になります。
まとめ:AI時代のプログラマー像
- コードを書く作業はAIに代替されつつある
- しかし「仕様を決める」「調整する」「システムを設計する」力は人間にしかできない
- AI活用にはセキュリティ・品質・依存のリスクがあるため、レビュー力がより重要になる
- オフショアは「量から質」へと変化し、上流で価値を出せる人材だけが生き残る
- 教育や学び方も「AIを扱える力」へとシフトしていく
- プログラマーは不要になるのではなく、役割と学び方が変わる
半年間Copilotを使ってみた僕の結論は、
「AIがプログラマーを消す」のではなく「プログラマーをエンジニアへ進化させる」 ということです。