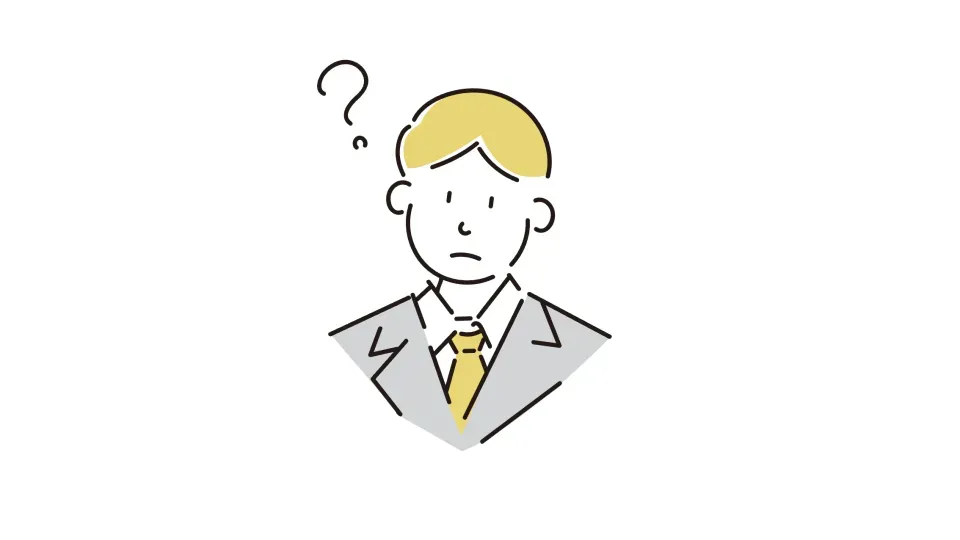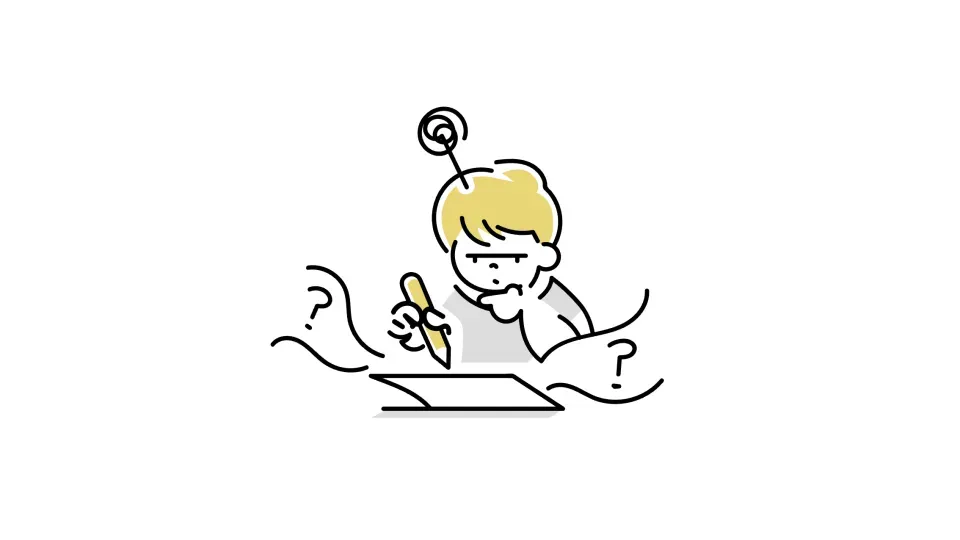現役SIerとして複数の大型プロジェクトに携わってきた経験から、 「これ、SIerなら誰でも共感するやつ…!」 という“SIerあるある”を10個まとめます。
「会議が多すぎる」「仕様変更が突然降ってくる」「背景説明が少なすぎる」… 一つでも当てはまったら、あなたは立派なSIer民です。
1. 会議が多すぎる
SIerといえば、まずは会議の多さ。 出社してスケジュールを見ると30分会議が8本──これはまだ軽傷。
新人の頃は「話聞くだけで給与もらえるなんて楽じゃん」と思っていましたが、 自分が進行側になると地獄が始まります。
- 会議のために資料を作る
- 会議のために進捗を“無理やり”作る
- 会議の内容をまとめて次の会議につなげる
会議のために働き、会議のために資料を作り、また会議が生まれる… まさに会議ループ。
2. 一度決まった仕様が“いつの間にか”変わっている
SIerあるあるで最も精神を削るのが仕様変更の突然降臨。
- 「昨日まで A 案だったのに、今日は B 案に変わっていた」
- 「なぜ変わったのか説明がない」
- 「そもそも現場に伝わっていない」
日本のSIerは“ITゼネコン構造”と言われるように、 判断が上層でなされ、下に降りてくる頃には情報が欠落していることも多い。
その結果、 「しれっと決まっている/しれっと方向転換されている」 という現場泣かせの現象が発生します。
3. 背景説明がなく、協力会社に“作業者感”だけが残ってしまう
SIerのプロジェクトは多くの場合、複数の協力会社が関わります。 しかし、仕事を依頼するときに背景説明をせず、「誰でもできる作業レベル」に粒度を落として依頼することが多いのです。
結果、協力会社の人は「機能を作ること」だけを目的としてしまい、本来の狙いやユーザー価値を意識できなくなります。
こうした背景共有不足が、最終成果物の品質低下やチームの温度差につながります。
SIerの下でSESとしては働いている友人の話を聞いたことがあります。 そこで彼が言っていて印象的だった言葉があります。
「今やっているPJはどういう目的があるのかが分からない。それを知りたい。」
その子はまだ20代で若く、エネルギッシュな人でした。 そういう若い人であれば、自分が協力会社なのか元請けなのかをそれほど意識せずに、 仕事の目的達成に向けて積極的に仕事をしてくれます。
ただし、若いうちからそのような情報に触れられず、言われたことばかりやる癖がついてしまうと、 「自分は協力会社の人間だから」という思考になり、結果的にSIerと協力会社の間に連帯感が生まれなくなるのだと思います。
これは、情報を十分に渡さない元請け会社に責任があると思うので、 可能な範囲で情報を渡すようにしたいですね。
4. 時間制契約の歪み
海外では、成果報酬型の契約が一般的です。
契約内容に沿って成果物を納品し、その品質や納期で評価されるため、効率的な働き方が求められます。
もちろん、成果が出せなければ契約終了や解雇につながるため、「残酷だ」という意見も少なくありません。
一方、日本のSIer業界では、完全時間制(いわゆる人月契約)が根強く採用されています。
これは「何人が何カ月間、その案件に稼働するか」で契約金額が決まる仕組みです。
この契約形態では、成果の有無よりも“時間を消化したかどうか”が評価基準になる傾向があります。
この仕組みには大きな弊害があります。
- 無駄な作業が温存される
「時間を使うこと」が目的化してしまい、本来不要な作業や資料作成が延々と続く。 - 非効率な進め方が改善されない
効率化によって作業時間が減ると、契約額も減ってしまうため、わざと工数をかける文化が生まれる。 - 成果より稼働時間が優先される
納品物の品質や完成度よりも、「稼働時間=価値」という錯覚が組織全体に染み付く。
例えば、ある案件で必要な機能が早く完成したとしても、「まだ期間が残っているから」という理由で細かい仕様変更や不要なドキュメント作成が発生します。
これは顧客・ベンダー双方にとって本来は非効率ですが、「人月契約」という枠組みの中では合理的に見えてしまうのです。
確かに、この仕組みは安定した収入を保証します。
プロジェクトが遅れても契約期間中は報酬が発生しますし、急な契約終了のリスクも低い。
しかし、その代償として仕事術は磨かれにくく、労働時間は長く、改善のインセンティブも働きづらいという現実があります。
結果として、業界全体を長期的な視点で見ると、生産性向上の機会が失われ、効率の悪さが慢性化してしまう――。
それが、私がSIer業界にいて強く感じる「時間制契約の歪み」です。
5. PJの成功は、実作業者のスキルに大きく依存する
プロジェクトの成功は、最終的にはマネージャーの手腕に左右される――。
これはSIerに限らず、あらゆる業界で通じる共通認識だと思います。
マネージャーが適切にスケジュールを引き、リスクを管理し、チームをまとめ上げる。
そうしたリーダーシップがあってこそ、プロジェクトはゴールへと近づきます。
しかし、SIer案件にはもう一つの大きな特徴があります。
それは、最終的な成果の品質が「実作業者」のスキルに大きく依存するということです。
理由はシンプルです。
SIer社員自身は、基本的に成果物を直接作らないからです。
設計書を書いたりコードを実装したりするのは、多くの場合、協力会社やオフショア拠点のエンジニアたち。
つまり、マネージャーやSIer社員は「作る人」に指示を出す立場であり、自ら手を動かすことはほとんどありません。
このため、いくらマネージャーが優秀でも、実作業者のスキルが不足していれば、プロジェクトは思うように進みません。
例えるなら、一流の監督がいても、選手がボールを扱えなければ試合に勝てないサッカーチームのようなものです。
仕様理解の不足や実装経験の浅さが原因で、想定以上に手戻りが発生し、スケジュールが大きく崩れることも珍しくありません。
もちろん、優れたマネージャーであれば、スキル不足をカバーする方法を模索します。
レビュー体制を強化したり、タスクを細分化して負荷を分散したり、教育コストを投下したり…。
しかし、それにも限界があります。
根本的に実作業者のスキルが不足していると、納期遅延や品質低下のリスクは高まり、顧客満足度にも直結します。
SIer案件の現場にいると、「誰が作業するか」がプロジェクトの成否を大きく左右することを痛感します。
これは時に、計画書や進捗表よりもはるかに重要なファクターです。
おわりに|SIerのリアルを知ることがキャリア戦略の第一歩
SIerは安定性や大規模案件の経験が魅力ですが、 構造的な非効率や閉鎖的な文化にモヤモヤする人も多い業界です。
もし「このままでいいのかな…」と感じるなら、 まずは情報収集し、
- 他社の働き方
- 自分の市場価値
- 将来のキャリアパス
を知るところから始めてみてください。
知ることが、迷いを減らし、 あなたのキャリアを“自分で選べるもの”に変えてくれます。