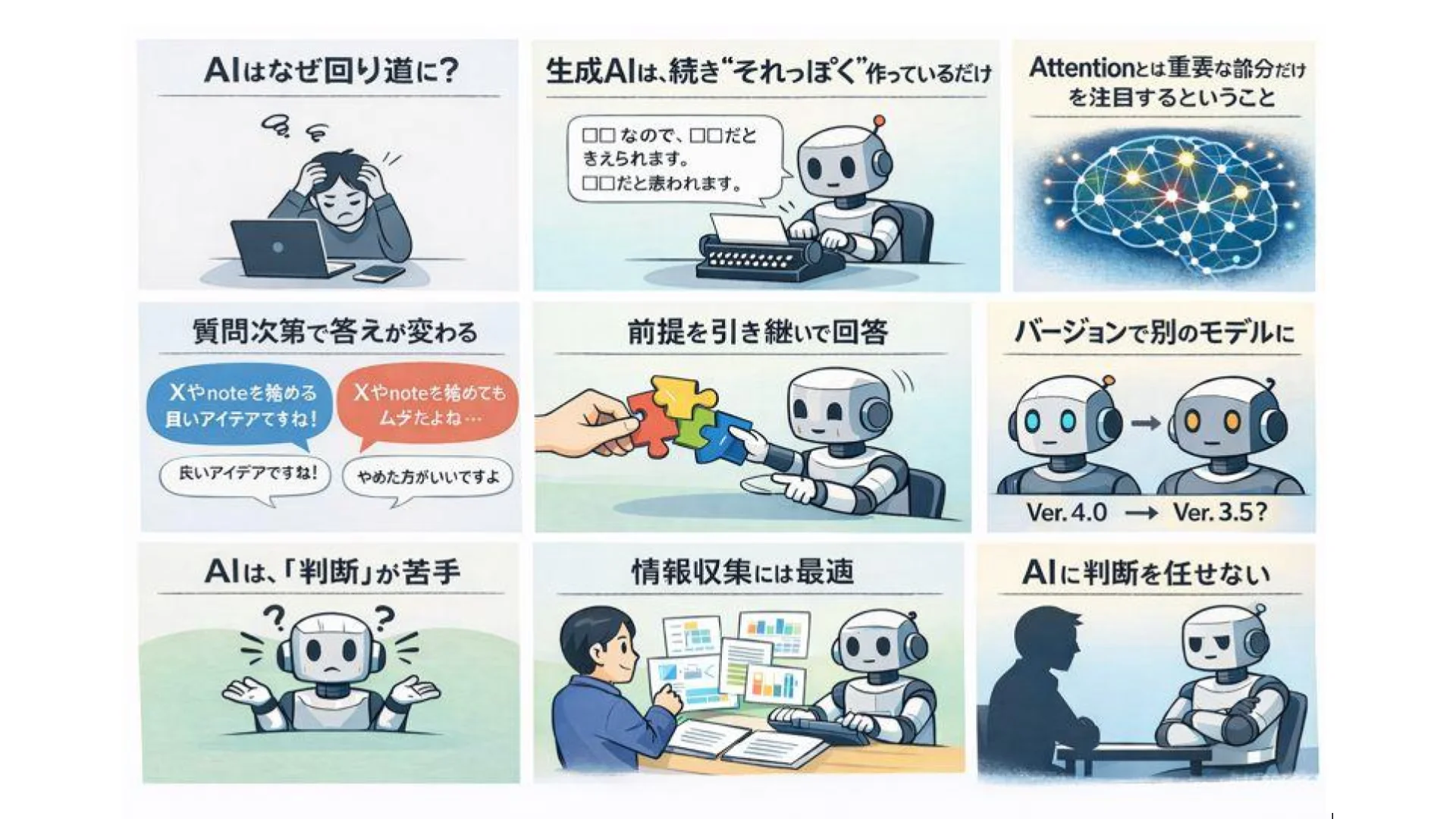ピーターの法則というものをご存じでしょうか?
ざっくり言うと、「人は自分の能力を発揮できなくなるところまで昇進してしまう」という理論です。
「プレイヤーとしては優秀でも、課長として優秀とは限らない。課長として優秀でも、部長として優秀とは限らない」というやつですね。
多くの組織では、プレイヤーとして優秀な人が課長に昇進し、課長として優秀な人が部長に昇進していきます。
ところが、もし昇進先で能力を発揮できなければ、その人はその役職に留まり続け、プレイヤーに戻ることもありません。
結果として「適材適所」が崩れ、組織全体のパフォーマンスが落ちる――これがピーターの法則です。
この話を聞いたとき、なるほどと思う一方で「業種や前提条件によって違うんじゃないか?」という疑問も浮かびました。
そこで、SIerという環境に限定して、シミュレーションができるWebアプリを自作してみました。
アプリの内容
- 100人の社員をランダムに生成
- 昇進方式を「実力(フラット)」または「段階的(一般的な昇進制度)」で比較
- 各レイヤー(SE、TL、PL、部長、役員)ごとに必要なスキルを定義
- 昇進後の平均スコアをグラフ化して可視化
スキル定義はもっと詳細化もできましたが、オッカムの剃刀的な考えでシンプルな粒度に留めました。
考察:ピーターの法則は正しいのか?
シミュレーションの結果、段階的昇進の方が平均スキルは高めに出る傾向がありました。
ただし、これはあくまでシンプルな前提と雑な粒度で行ったものなので、完全に信頼できる数字ではありません。
感覚的には「段階的昇進は大きな失敗はしにくい。一方で、フラット昇進は結果がバラつきやすい」という印象です。完全ランダムだとさすがに崩壊しやすい。
また、このシミュレーションでは「才能は最初から固定されている」という前提を置きましたが、現実では環境によって人は育つことも多いはずです。
実務の世界では、昇進後の学習や経験が能力を補う部分もあるので、その点を加味すれば結果は変わってくるでしょう。
評価軸の難しさ
今回は単純に「必要スキルの平均合計値」で評価しました。
しかし、実際の組織で重要なのは平均点よりも「上層部の出来」なのかもしれません。
- 下層のスキル合計が高くても、上層部が機能していなければ組織は動かない
- プロジェクト成功に直結するのは、やはりマネージャー層の力量
と考えると、役職ごとに重み付けをした評価のほうが、現実に近いのかもしれません。
まとめ
ピーターの法則はシンプルで面白い理論ですが、現実に当てはめると前提条件の設定次第で大きく結果が変わります。
今回のシミュレーションでは「段階的昇進」がやや有利という結果になりましたが、実際には昇進後の成長や役職ごとの重要度も考慮すべきでしょう。
つまり――
ピーターの法則は「話半分で面白がる」くらいがちょうどいい。
むしろ、それをきっかけに「昇進制度や評価制度をどう設計すべきか」を考えるほうが価値があるのかもしれません。