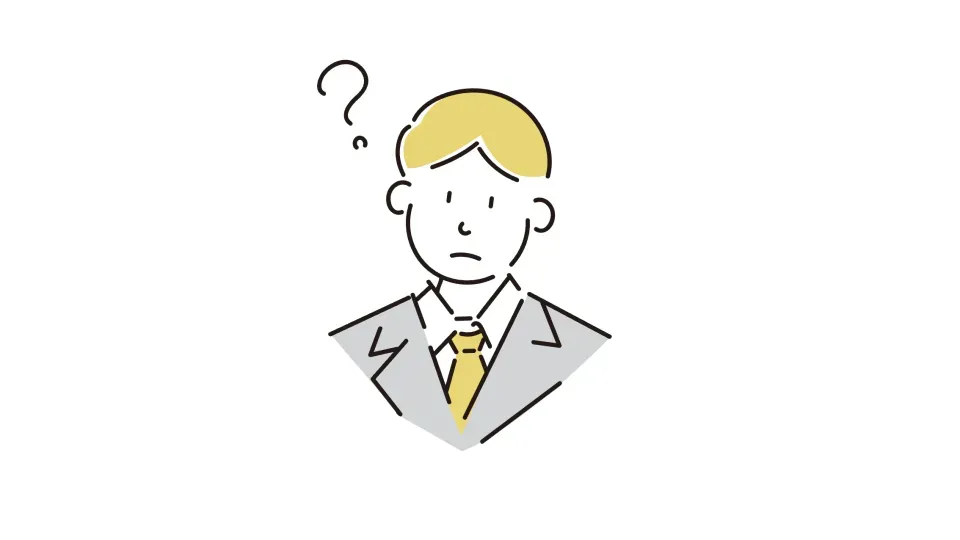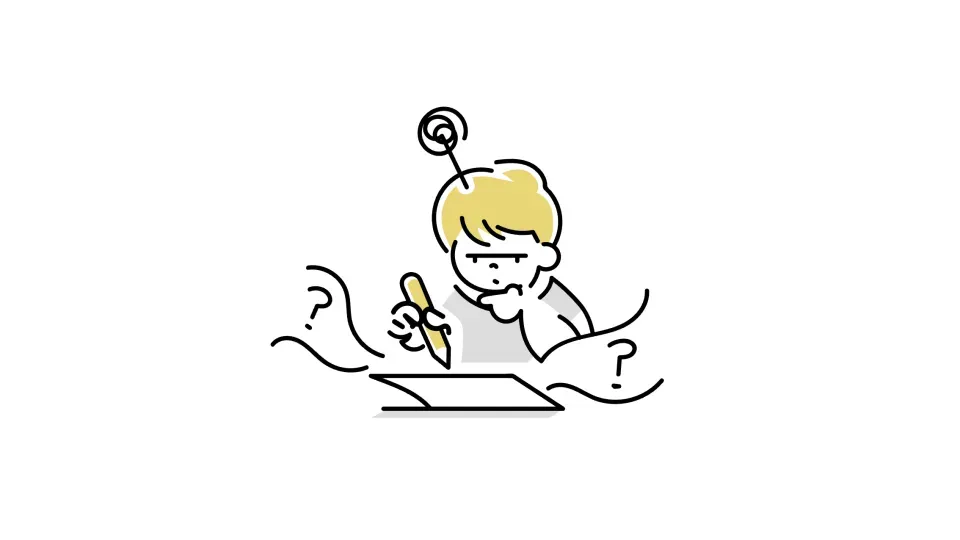SIerで2年目を迎え、ようやく仕事が少しずつ安定してきました。 スキルが急成長したわけではありません。 でも、“仕事を回す仕組み”を整えるだけで、日々の負担がかなり減ることに気づきました。
この記事では、私がこの1年で実践して効果があった「仕事を安定させる仕組み」と、 まだ課題だと感じている部分を率直に振り返ってみます。
✅ SIer仕事術5選
1. タスクは「脳で覚えない」
SIerの現場では、メール・チャット・会議・対面のふとした会話で、タスクが無限に湧いてきます。 なので、ほんのちょっとしたタスクであっても、メモを取らないと10分後には忘れてしまいます。
重要なのは、「覚える」のではなく「記録する」ことを習慣にすること。 ツールは何でも構いません。 大切なのは「すぐに書ける」「すぐに消せる」こと。 ToDoアプリでもテキストメモでも、最速で更新できるものを使うのがおすすめです。
逆に、Excelはあまりおすすめしません。 理由は単純で、「開くのが遅い」「SIer現場では、常に大量のExcelを開いている」から。 タスクを分析したいときだけExcelを使い、日常管理はもっと軽いツールに任せた方が現実的です。
2. 優先順位は「期日」「重さ」「影響度」で決める
配属当初は、単純に期限が近い順で仕事をしていました。 ですが、最近は期日に加えて、タスクの重さや影響度で決めることが増えてきました。
というのも、2年目にもなると、これと決まった期日は誰かから提示されるものでもなく、自分で決めるものだからです。 その期日を決めるのに、タスクの目的を理解する必要があり、それがタスクの重さや影響度として現れているのだと思います。
抽象的な話をしましたが、タスクの期日というのは、タスクの目的を理解していれば、提示なれなくとも分かるものです。 ので、期日で決める、とのうが少しずれている、という感覚になりますね。
3. 証跡を残す
SEとしての基本かもしれませんが、作業の証跡(エビデンス)を残すことを常に意識するようになりました。 これ大学生の時には分からなかった感覚ですが、SIerの仕事では各工程にレビューというものが絶対あります。 設計書書いたらレビュー、製造したらレビュー、テストしたらレビュー、、、というふうな感じです。
そのため、自分のした作業を証明するために証跡を残すということが求められます。 で、これは人に見せる可能性がある作業は全て、証跡として残しておくほうが無難です。
脱線:自分の研究室時代の話
話ずれますが、研究室では教諭が詳細まで学生の作業のレビューをすることがなかったのですが、 これって普通なんですかね? 今となっては、誰のコードレビューも受けないまま、どういう処理を組んだのかだけを教諭に説明して、 結果1本論文発表しましたが、 あれが本当に正しいかどうかは誰も保証できないなんて、結構やばい話だなと思います。 コード組んだ自分が言うのもなんなんですが 笑
4. 説明資料は「美しさ」より「速さ」
障害報告や課題説明の際、口頭や文章だけで伝えるのは限界があります。 そのため、多くのSEはExcelやPowerPointを使って事象をビジュアル化します。
以前は「丁寧で分かりやすい資料」を作ることに時間をかけていました。 しかし今は、“スピードと伝達効率”を最優先にしています。
大学で学んだ発表資料のような凝ったデザインは不要です。 3秒で理解できる図や表を作ることが、現場では最も価値があります。
デザインにそんなに凝っていたら、逆に暇なんじゃないかと思われる気がします。もちろん早く綺麗な資料が作れる人であればいいんですが、速さと綺麗さはどうやってもトレードオフなので、最もいい塩梅の資料を作ることが大切です。
とはいっても、大学時代で培ってきたパワポ術を急に捨てるのは勇気がいると思います。自分が実践したコツとしては、保守性が高く、すぐに作成できる代わりに美しく見える型だけを使い込むことです。
時間がかかり美しく見える型は、社会人には求められないことが多いので捨てましょう。
そういうのが専属でやりたいなら、そういう仕事がありますしね。
うまくできていないこと
1. 報告が遅れる
問題が発生しても、「もう少しで解決できるかも」と思い、報告を先延ばしにしてしまうことがあります。
あるいは、「怒られるのが怖い」という気持ちも影響しているのかもしれません。
実際は、想定しているほどは怒られないもんですが。
さらに、「どこまでのレベルの問題を報告すべきかが分からない」ことも一因でした。
報告したら説明を求められて、それで作業が遅れるくらいなら報告しない方がいいのでは?と、無意識に思っていたこともありますと振り返ります。
ただ最近は、「とりあえず一報入れる」ができるようになってきました。
報告が遅れるより、上司に状況を認識してもらうことのほうがずっと重要だと学びました。
2. 忙しそうな人に声をかけづらい
「あの人、今忙しそうだし…」と思って相談や報告を後回しにしてしまうことがあります。
でも、それを気にしていたら永遠に仕事は進みません。
相手が忙しかろうと、相談・報告する側の責任を果たすことが何よりも大事だと最近思います。
「タイミングを見計らって報告しよう」なんてできるほどのスキルもないので、今は気にせず伝える姿勢を意識したいです。
3. タスクの放置と視野の狭さ
自分で抱えたタスクを何も言わずに放置してしまうことがあります。
それ自体が必ずしも悪いわけではないのですが、上司やチームへの情報共有ができていないのが問題です。
今となっては、「2週間後から着手でも良いですか?」と相談できるようになってきました。
新人の頃には一回り上の上司相手に到底言えなかったことですが、これからは積極的に調整の会話をしていこうと思います。
4. 愚痴を漏らす
これはなかなか難題です…。 今のところ明確な対処法は見つかっていませんが、 少なくとも愚痴を言っても状況が好転することはないので、注意していきたいところです。笑
でも、自省し過ぎても潰れるだけなので中道が大切ですね。
5. 自分のためになる仕事を選ぶこと
新人時代は「仕事は選ぶな」と言われてきましたが、実際に活躍している人を見ていると、
目立つ仕事ややりがいのある仕事を選び、雑用は他人に任せている印象があります。
一方で、地道に仕事をこなしている人は、私から見ればとても好印象なのに、
会社の上層部には存在すら認識されていない、という残念な現実もあります。
私自身も会社員である以上、ある程度は社内の“見せ方”や“政治力”を身につけていく必要があると感じています。
まとめ
うまくできていること、できていないことの両方を挙げてみると、まだまだ改善の余地はあるものの、
確実に自分の中で成長している部分もあることに気づきました。
「報告の速さ」や「タスク管理」、「見せ方」など、社会人としての土台をもっと強化しつつ、
自分らしい仕事のスタイルを確立していければと思います。