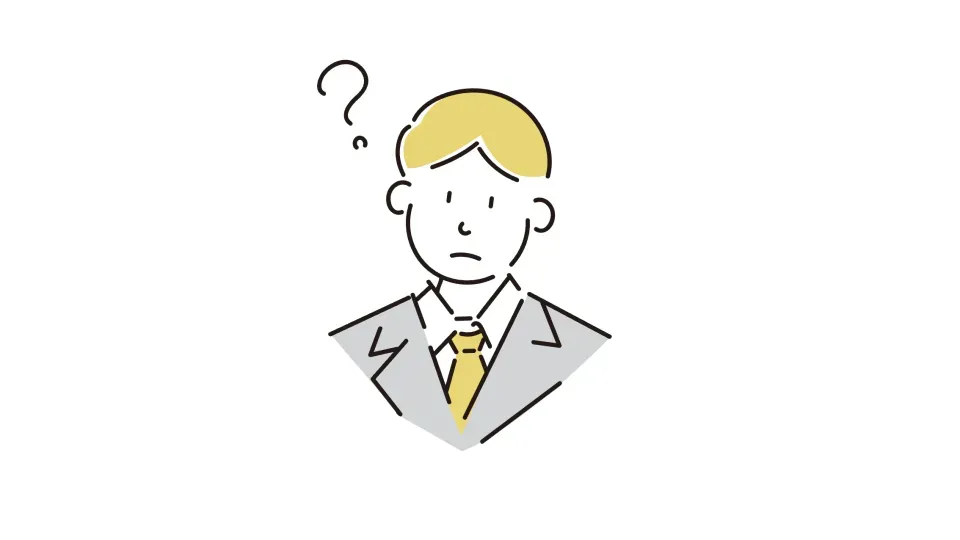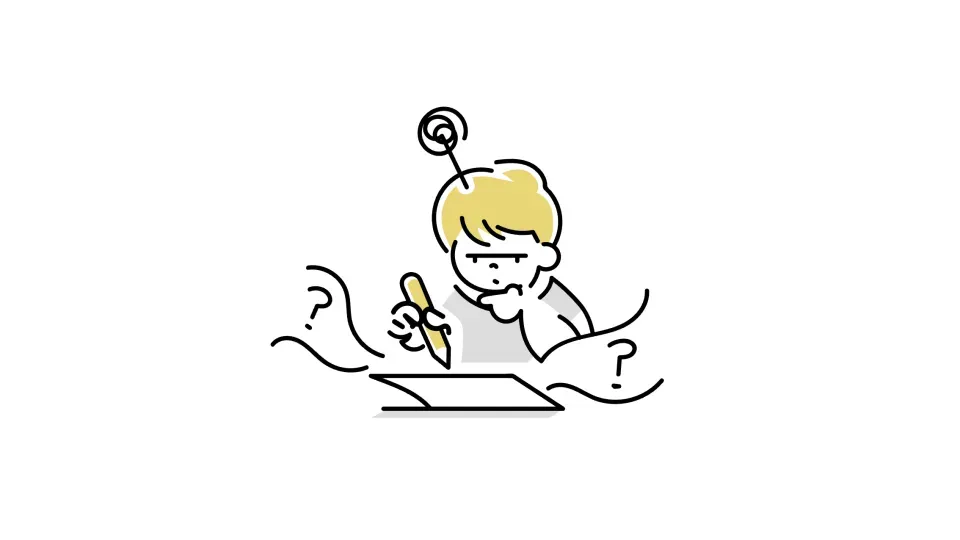あなたの職場、ドキュメントって生きてますか?
共有フォルダには大量の手順書が眠っているのに、結局“人に聞く”ほうが早い。 誰かが苦労して残したナレッジが、いつの間にか埋もれていく。 なぜこんなにも、ナレッジは定着しないのでしょうか。
この記事では、SIerの現場で感じた「ナレッジが残らない構造」と「少しだけ改善できる方法」をまとめました。
ナレッジとは何か?──「知ってる人しかできない」を減らす仕組み
ナレッジとは、過去の業務経験を共有するための情報です。 たとえば、以下のような内容が該当します。
- ソフトウェアのセットアップ手順
- システム障害時の対応フロー
- 定常作業の実施手順
つまり、「次に同じ作業をする人が困らないように」残す知識のことです。
しかし現場では、この“当たり前”の文化を定着させるのが非常に難しい。
ドキュメント形式は様々ですが、職場でよく見かけるのは以下の通りです。
- Excel
- テキストファイル
- Word
- PowerPoint
個人的には、キャプチャ付きの手順ならExcel、テキストだけならtxtが最適です。
Wordは構造化がしづらく、PowerPointは一枚あたりの情報量が少ないため、ナレッジにはあまり向いていません。
なぜナレッジが残らないのか?
① すぐに古くなる
ITの世界では、ソフトやツールのバージョンが頻繁に変わります。
数ヶ月前に作ったマニュアルが、もう使えなくなっていることも珍しくありません。
iPhoneのような完成度が高いシステムであれば、多少OSが変わっても古い手順書のままで対応できることがあります。
一方で、中小企業が開発したソフトは話が別です。 私が経験した中で最悪だったのは、「外部ソフトのパスをハードコーディング」していたシステムです。ソフトがアップデートされパスが変更されるたびに、コードの修正が必要になるという状態でした。 そのため、中小企業が開発したソフトでは古いマニュアルを転用することは、不可能になる場合も多々あります。
こういった状況は、そもそもソフトウェア自体の「保守性の低さ」に原因があります。 つまり、この問題の本質は、ドキュメントではなくソフトウェア側の設計にあると言えるでしょう。
② 評価されない
ナレッジを残しても、上司の評価に直結しないことの方が多いです。 勿論お礼を言ってもらえるかも知れませんが、多くの上司は むしろ「それより自分のタスクを進めて」と思っている場合が殆どでしょう。
これは自分が上司の立場になって考えると自明です。誰かにタスクを渡して、「終わった?」と聞いた時に、「タスクは終わりましたが、今手順書を作っていて、別の仕事ができないです。」と言われたら、「それはいいから次これやって」となるのが普通でしょう。(もちろん“どっちもやれ”が本音ですが。笑)
結局、社員のモチベーションは“評価構造”に左右されます。 「周りの誰かが助かる」より「上司に褒められる」ほうが優先される。 この構造が、ナレッジ共有を阻む最大の壁です。
③ 埋もれる
せっかく作っても、フォルダ階層の奥に眠り、誰にも見つけてもらえない。 SlackやTeamsで共有しても流れていく。 社内Wikiがあっても、更新頻度が低い。
最近では、Copilotなどの生成AIに社内ドキュメントを読み込ませ、埋もれない仕組みを作ろうとする動きもあります。 もしAIがTeamsのチャットやドキュメントを横断的に理解できるようになれば、もはや“最強のPMO”になるかもしれません。
④ 責任リスクがある
ドキュメントを書いた人が間違っていた場合、「誰が書いたの?」と責められる。 この心理的リスクが、「書かないほうが安全」という空気を生みます。
⑤ 作成者の負担が大きい
ナレッジを書ける人=現場を理解している人です。 つまり、一番忙しい人ほどドキュメントを書く余裕がない。 結果、できる人が損をする構造になってしまうのです。
余談:ナレッジが生きるのは“頭の柔らかい職場”
年次の高い人の中にも、柔軟に進めるよう指示してくれる上司もいます。
ただ、頭が硬い人が一人でもいると、若手は「自分で考える」意欲を失っていく。
ナレッジが形骸化する職場には、そんな“心理的な硬直”も少なからず影響している気がします。
現場で感じた“うまくいくチーム”の共通点
一方で、ナレッジ文化が根づいている部署もあります。 友人の部署では、新人研修の中に「ナレッジ共有時間」が組み込まれていました。 自分が学んだことをその日のうちに文書化し、週1でレビューされる仕組み。
新人時代から、ナレッジを残すことを当然の義務として教育しておけば、 確かにそれが習慣になって、いい部署になりそうだなとも思いました。
結果として、「書くこと」が当たり前の文化になっていました。
ナレッジが数TBに達するほど蓄積され、誰が見ても情報が整理されている。
羨ましいくらいに整った仕組みです。
まとめ
ナレッジ共有は、怠慢ではなく“構造の問題”です。 だからこそ、個人単位でできる工夫を積み上げるしかありません。
未来の自分を助けるつもりで、今日の作業を一行でも残す。 それが、地味だけど確実な「強いチーム」への第一歩だと思います。