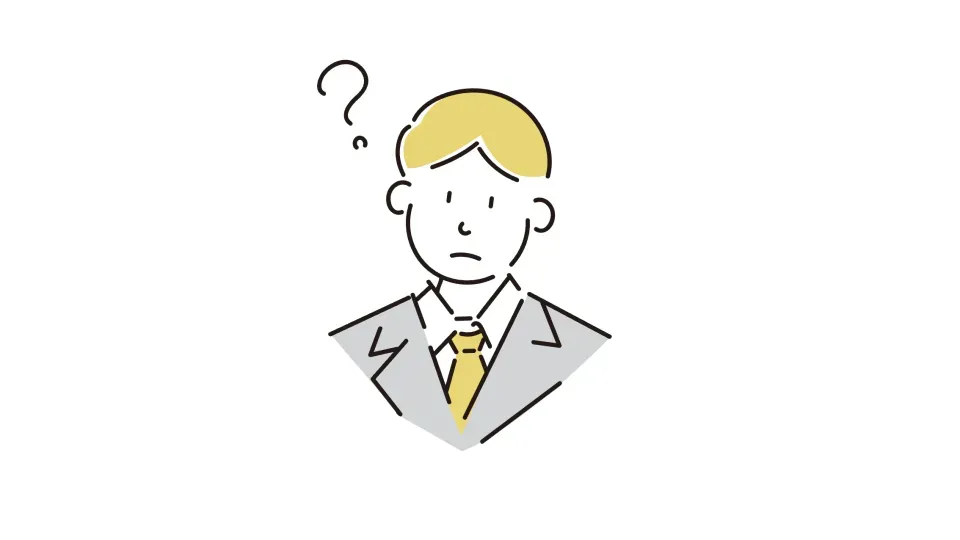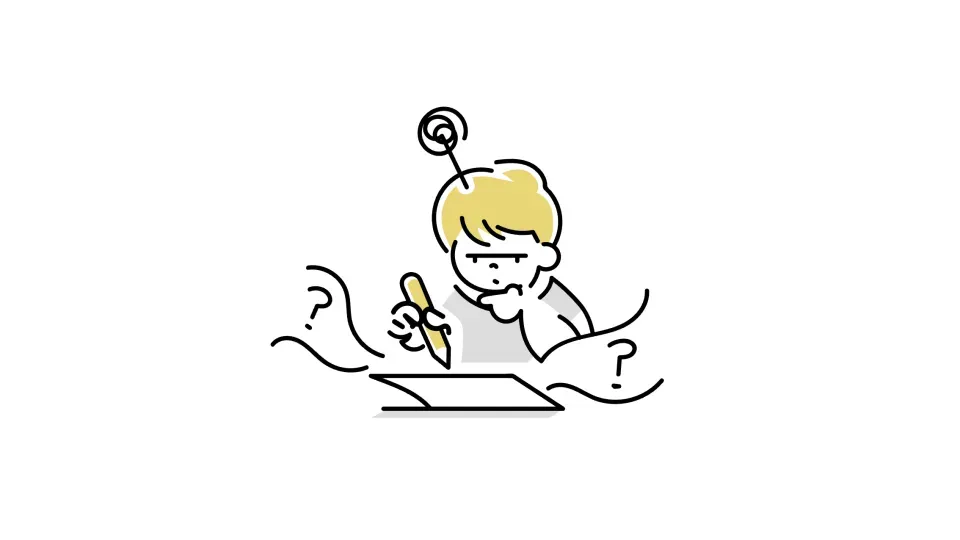ある平日の定時後。
友人との予定が迫ってきて「そろそろ帰りたいな」と思っても、目の前には終わっていないタスクが残っている。
周りの人は普通に自分の予定で帰っていくのに、自分だけが椅子から立ち上がれない。
「定時を過ぎても、仕事を優先するべきなのか?」
頭では「今日は帰りたい」と思っているのに、足が動かない。
そんな感覚を覚える若手SEは、少なくないはずだ。
この記事では、SIerで働きながら感じた
“予定を自由に入れられない”という働き方の構造
と、そこからどうやって“自分の時間”を取り戻すかを考えていきたい。
1. SIerでは、なぜ「予定が入れられない人間」が量産されるのか
若手SEとして働いていると、次第に“予定を入れづらい身体”になっていく。
これは自分の段取りが悪いわけでも、意思が弱いわけでもない。
SIerという働き方そのものが持つ“構造”の問題だ。
予定を入れづらくなる背景には、次のような要因がある。
-
納期とタスクが“人”に紐づきすぎている
担当者が帰れば、その日の対応は止まる。
周囲も「今日だけなんとかして」と依存しやすい。 -
障害対応が予定を破壊する
障害は予告なく起きる。
そしてなぜか、緊急対応は若手の時間を奪う方向に流れる。 -
属人化が強く、代わりがほとんど育たない
引き継ぎが形式的で、本当の意味で代替がきかない。
「その人がいないと回らない」状況が若手にも平気で起きる。 -
極めつけは「休むなら、代わりを探しておいてね」という文化
本来は管理者がやるべき調整が、なぜか末端に落ちてくる。
こうした積み重ねが、若手の“予定の自由”を静かに奪っていく。
2. 予定が入れられないと、人間関係がじわじわ壊れていく
予定は「確実に守れる」前提がないと入れられない。
水曜の夜、友人に「飲まない?」と誘われたとする。
答えたいのは山々なのに、
「たぶん大丈夫だけど、仕事入ったら無理かも」
としか言えない。
そしてキャンセルが2回、3回と続けば、友人はこう思う。
「あいつはもう誘っても来ないやつだ」
僕自身、何人かとはそのままフェードアウトした。
予定を入れない生活が続くと、
「自分の人生のハンドルを他人に預けている」
ような感覚がじわじわと強くなる。
これは仕事のストレスとは別の、静かな喪失感だ。
3. 社用携帯が“心をオフにする”時間を奪っていく
仮に予定通り出かけられたとしても、問題は終わらない。
ポケットの中で社用携帯が震えた瞬間、
オフのつもりだった心が一気に仕事モードに引き戻される。
通知には「どこにいます?」
あるいは「至急確認したいことが」と書かれている。
友人の前で笑っていても、心はずっとソワソワしている。
その時間は“遊んでいる風”であって、本当には休めていない。
半年以上、残業ギリギリ45時間で働き続けた頃、ふと思った。
「俺、ここまでして働く理由ある?」
やりがいよりも、ただ時間が削られていく感覚のほうが強かった。
4. 誰も望んでいないのに、なぜこの働き方が続くのか
不思議なのは、
この働き方を心から望んでいる人が誰ひとりいないことだ。
上司だって休日出勤を命じたいわけじゃない。
「予定空けておいてね」と言いたくて言っているわけでもない。
ただ、顧客対応や評価、人事制度、社内慣習といった
“変えにくい仕組み”が積み重なり、
結果として今の働き方が温存され続けている。
誰も悪くないのに、みんなが疲弊する。
それがSIerの「構造的ブラックさ」だと気づいた。
そしてこの状態で、良いシステムを作るのは難しい。
“モチベーションが削られる仕組み”で回っている以上、 良いアウトプットが生まれるはずがない。
5. 若手がこの環境で“人生を守る”ためにできること
SIerが急にホワイトになることはない。
だからこそ若手が身につけるべきなのは、「対処」ではなく“戦略”だ。
たとえば、次のような工夫は小さく見えて、意外と効果が大きい。
-
自分の予定に優先順位をつける
すべてを死守するのは不可能。
ただ「ここだけは守りたい」という日は、朝のうちに宣言しておくと流れを変えられる。 -
担当範囲をはっきりさせる
曖昧だと、できる人のところにタスクが雪崩のように集まってくる。
境界線を言語化することは、自分の時間を守ることでもある。 -
“できない”を早めに伝える
これは逃げではなく、キャパシティのコントロール。
限界を超えてから言うより、事前に伝えるほうが圧倒的に信頼される。 -
属人化を避ける
情報やスキルを共有することは、
“誰かに仕事を渡せる状態=自由時間を買う行為”でもある。
ほんの小さな工夫でも、自分の人生に対するコントロール感は大きく変わる。
「仕組みは変わらないから、何もできない」ではなく、
変えられるところだけでも静かに変えていくことが大切だ。
6. もし自分が管理者だったら、絶対に変えたいこと
管理者の立場になったとき、僕は決して部下にこう言いたくない。
- 「休日、空けといてね」
- 「代わりを探しておいて」
- 「予定より仕事だよね?」
でも、これを言わずに済ませるには、“個人の優しさ”ではなく、
仕組みと文化そのものを作り変える必要がある。
まず、属人化をできるだけ減らし、特定の人にタスクが集中しないようにする。
予定の調整はマネージャー側が主体となって行い、若手に丸投げしない。
さらに、緊急対応が頻発する原因を振り返り、事前の仕組みで減らしていくことも重要だ。
そして何より大事なのは、
プライベートを尊重するチーム文化を“当たり前の空気”として根づかせること。
休む日を言いづらい雰囲気をなくし、予定を大切にできる環境を整えたい。
自分がツラかったことを、次の世代に引き継ぎたくない。
そのために変えるべきは、人ではなく“仕組み”と“空気”だと思っている。
結論:仕事も人生も、どちらも“自分の時間”でできている
仕事とプライベートは対立するものではなく、
どちらも“自分の人生の一部”だ。
もちろん、予定が狂う日もある。
急な対応が必要な時もある。
それでも、譲れない軸をひとつだけ持っておきたい。
「自分の人生は、自分のものだ」
会社の事情や誰かの機嫌に飲み込まれたくない。
せめてこの言葉だけは、胸ポケットにしまっておきたいと思う。