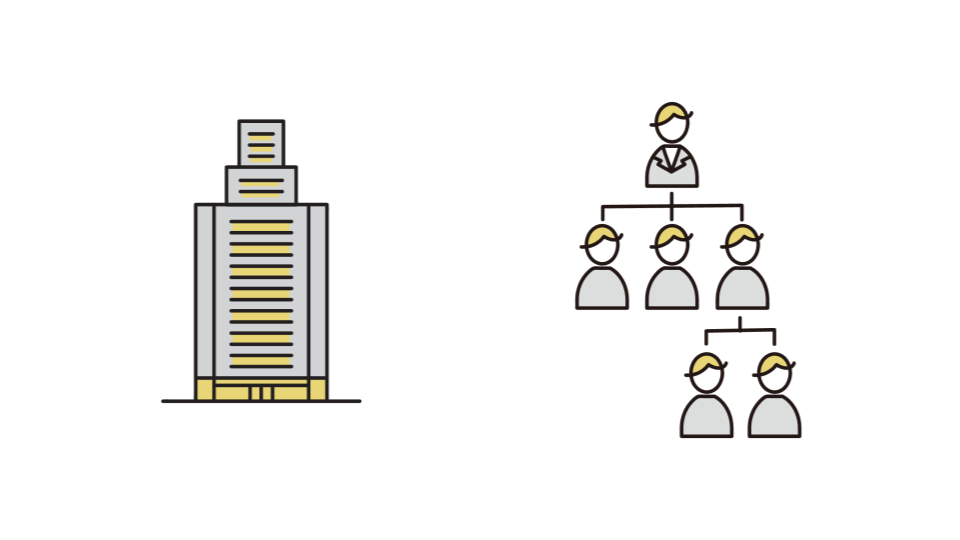
大企業で働いて感じたこと
投稿日: 2025-05-11 | カテゴリ: 雑談社会人になって、気づけば1年が経ちました。 私は最終的に、比較的大規模なSIerに就職しましたが、新卒時の就職活動では、ベンチャー系のSIer(おそらくPMO業務が中心)、 Webマーケティング企業、自社開発のソフトウェア企業など、規模も業態もさまざまな会社を見て回っていました。 正直なところ、小規模な会社に飛び込むべきかどうか、本気で悩んでいた時期もあります。
「新卒ではベンチャーに行くべきか?それとも大企業か?」という問いに、明確な答えは出せません。
ただ、自分が実際に大企業で1年間働いてみたことで、見えてきたこと、感じたことがいくつかあります。
本記事では、その経験をもとに、大企業で働くことのリアルを記してみたいと思います。
できる仕事の幅が広い
まず、大手SIerに入って最初に感じたのは、「とにかく関われる仕事の幅が広い」ということです。 イメージとして、ベンチャー企業は色々なことができる一方、大企業では決められた役割だけを黙々とこなすもの、という先入観がありました。 しかし実際には、そのような単純な構図ではありませんでした。
確かに、伝統的なSIerらしい「業務システム開発」などは主要業務の一つですが、それに限りません。
たとえば、データ分析業務、自社プロダクトの企画・開発、生成AIの活用、PMOとして他社のプロジェクト支援に入る仕事、あるいは他社開発の一部を請け負うようなワーカー的立場の業務まで、実に多岐にわたる選択肢があります。
もちろん、同時並行で全てに関わることはできませんし、望んだからといってすぐに異動できるわけでもありません。
それでも、「自分はこういう仕事がしたい」としっかり上司に伝え、また周囲に発信していくことで、希望に近いキャリアを描いていくことは十分可能だと感じています。
スピード感はやっぱり遅い
これは入社前のイメージ通りかもしれませんが、大企業はやはり意思決定のスピードが遅いと感じます。 その要因としては、大きく2つあると思っています。
- 判断ができる人に情報が届くまでの“伝言ゲーム”が長い
- 確認作業がとにかく多い
それぞれ、少し詳しく書いてみます。
1. 伝言ゲームが長い
たとえば、2次受けの現場にいるプログラマーが、開発中に「設計書通りに実装できない」という問題に気づいたとします。 そのとき、まずは1次受けであるSIer社員にその旨を伝えますが、たいていの場合、その社員には方針を決定する権限がありません。
そのため、社員はプロジェクトリーダー(PL)に報告し、さらにPLも判断できない内容であれば、プロジェクトマネージャー(PM)へと話が上がっていきます。
場合によっては、PMの上である部長や役員クラスの承認が必要になることさえあります。
このように、たった一つの判断を仰ぐにも、情報が階層的に伝達される“伝言ゲーム”を経る必要があり、結果として対応スピードが大幅に遅れてしまいます。
さらにやっかいなのは、こうした階層構造の中で「これでは判断できない」と差し戻されることが珍しくないという点です。
報告や相談が上の立場に届いたとしても、内容が不十分だと判断されれば、再度調査や資料の精査を指示されることになります。
これはメンバー⇔PLや、PL⇔PMの間に限らず、あらゆる上下関係で起こり得る話で、最終的には現場レベルまで再確認が必要になり、
調整とやりとりが何度も行き来する事象が発生します。
一度で済まないこのやりとりが、さらなる時間のロスにつながります。
2. 確認作業が多い
もう一つの問題は、「確認作業の多さ」です。
たとえば、顧客から「仕様Aを変更してほしい」という依頼が来たとします。 それを受けたPMは、その変更がシステム全体や他の機能にどんな影響を与えるかを確認する必要があります。 そこで、影響調査をチームのメンバーに依頼するのが一般的な流れです。
しかし、この調査が思った以上に大変なのです。
なぜなら、該当する仕様が作られた背景には過去の経緯や複雑な事情が絡んでいることが多く、すんなり答えが見つからないからです。
仮に、その分野に詳しい先輩社員に聞いてみたとしても、返ってくるのはこんな言葉だったりします。 「たしか当時はそういう仕様だったと思うけど、今どうなってるかはちょっと分からないな、、、」
この「当時はそうだった」という曖昧な返答が出てしまった瞬間、調査結果は“保留”扱い。 PMにそのまま報告しても、「じゃあ今はどうなの?」と詰められてしまい、再調査が必要になります。
結局、自力で過去の設計資料、仕様書などのドキュメントを読み直し、関係者に地道にヒアリングを行いながら、少しずつ情報を集めていくことになります。
ようやく「おそらくこうだろう」という80%くらいの確信を持って再報告しても、「で、100%の確証はあるの?」とさらに詰められる。
もし上司が非常に有能な“プレイヤー型”であれば、残りの20%を一緒に詰めてくれるかもしれません。
しかし、そうでなければ、限られた自分のリソースの中で100%の確度を求められるのは、正直かなりきついです。
しかも当たり前ですが、その確認作業に自分のリソースを全振りして別のタスクを疎かにすれば、それはそれでまた指摘されてしまう。
こうした背景があるため、大企業における意思決定のスピードが遅くなるのも、ある意味では必然だと感じています。
「学び切ってから転職」は幻想かもしれない
就職活動中には、「その会社で学び尽くしてから次に進めばいい」という意見をよく目にしました。 当時の自分も、そんな考え方に共感していた記憶があります。
でも、今の私は、それは現実的ではないと思っています。
SIerの仕事というのは、アルバイトのように「一つの仕事を覚えたらそれで終わり」というものではありません。
案件ごとに顧客も違えば、業界も違い、使用する技術もプロセスも異なります。
言い換えれば、毎回が“別の仕事”なのです。
そんな中で「すべてを学び切る」のは、ほぼ不可能に近いと思います。 だからこそ、ある程度の経験と学びを得たら、「次に進む」という選択をしても、決して早すぎることはないと感じるようになりました。
まとめ
ここまで色々と書いてきましたが、私はまだベンチャー企業で働いたことがありません。 その意味では、比較対象として適切でない部分もあるかもしれません。 とはいえ、大企業で1年間働いてみて得たリアルな実感は、新卒の就職活動において少しでも参考になるのではと思っています。
悩む時期だとは思いますが、どちらを選んだとしても、最終的に自分次第。
選んだ環境でどう動くかが、一番大事なのかもしれません。
読んでくださって、ありがとうございました。
